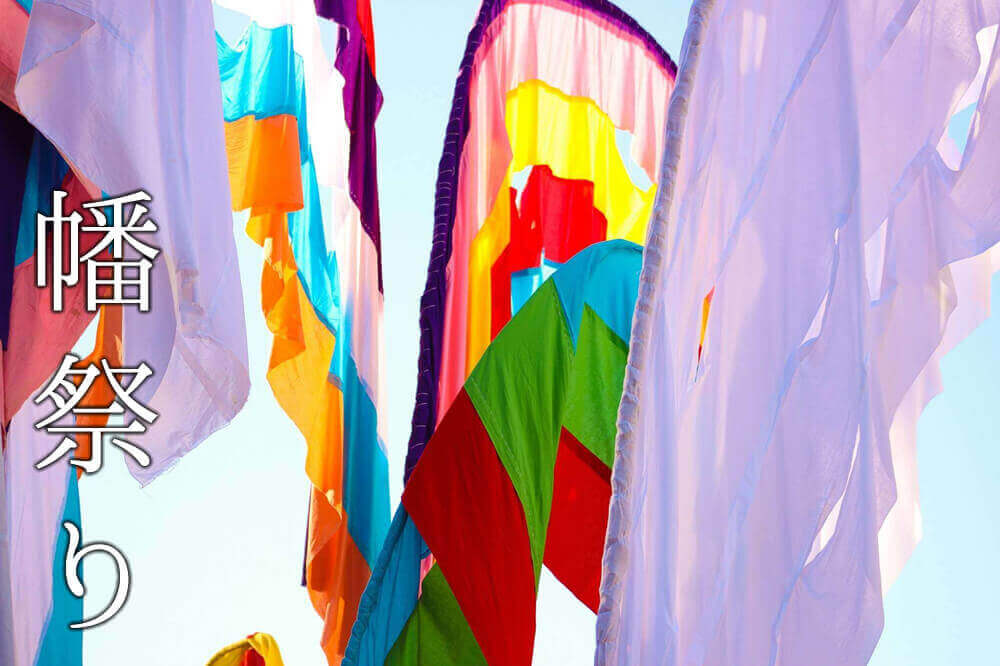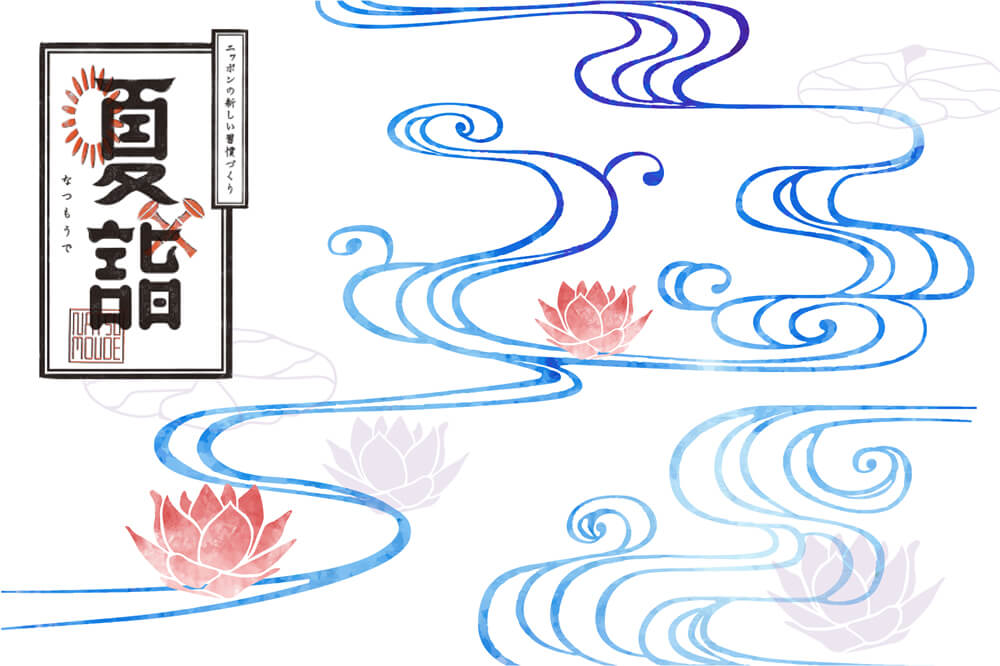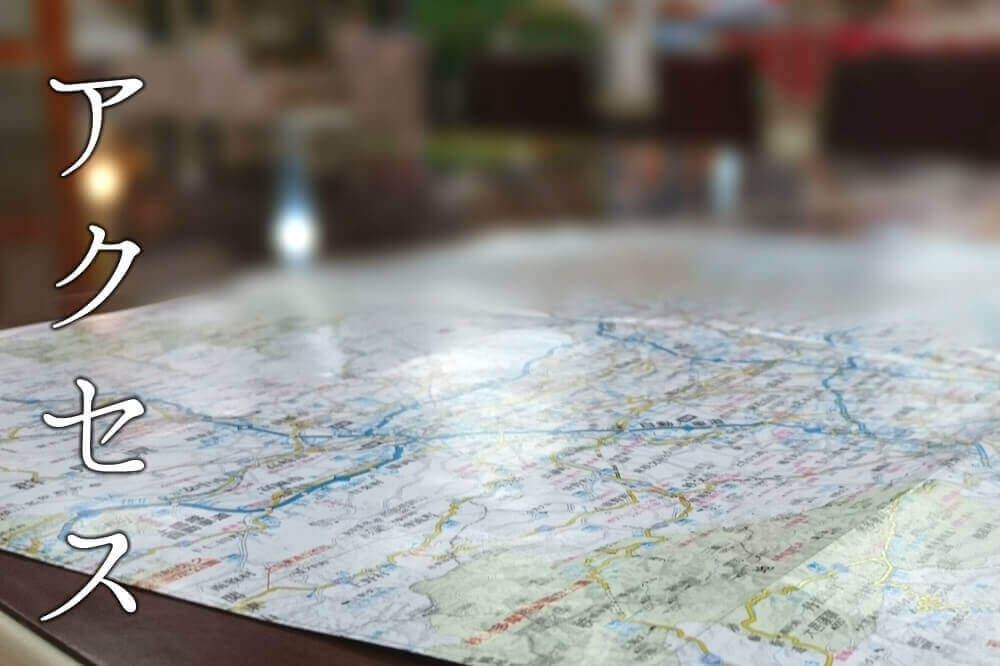木幡の幡祭りHatamatsuri

前夜祭
【 水垢離 】(折越堂社)(当番の堂社)(二の鳥居手水屋)
出立式
【 幡競争 】(木幡第一小学校)
出立
休憩・昼食
(参宿所)出立
鷹取場
羽山神社
【 胎内くぐり 】解散式
(本社)木幡の幡祭りは、五色に彩られた百数十本の五反幡を押し立てて法螺貝を響かせ、阿武隈の山間の道をぬって木幡山をめざす「木幡の幡祭り」は、師走の風物詩として全国に知られた祭礼です。
溯ること約950年前の「前九年の役」で陸奥国領袖の安倍頼良と征夷大将軍源頼義が戦った故事に因って、神仏の加護を崇敬する郷土民が勇壮な平安絵巻を継承してきた祭りです。
前9年の役天喜3年(1055年)天皇の命を受け陸奥征伐に出向いた源頼義・義家父子ら官軍勢は戦いに敗れわずか数騎で逃れ木幡山にたてこもり、神社に戦勝を祈願したとされます。
安倍の頼時は貞任・宗任を従え伊達信夫に出向き陣を構えた。その夜折からの雪で山上の木は全て源氏の白旗のようになり、貞任・宗任らの目には官軍が多数いるかに見え、戦わずして引き返してしまった。
これが陸奥鎮定の原因となり、朝廷に奏したところ天皇はこの山を「木幡山」、山裾の別当寺院を「治陸寺」(陸奥を治める)とせられ後冷泉天皇宸筆の額を賜ったとされております。
その後、神仏の加護を深く信ずる郷土民は、この縁起を「幡祭り」とし、950年に渉って承けつぎ今日に至っています。


幡祭りと言えば幡行列が有名ですが、祭のもう一つ重要な役割を成すものとして「羽山籠り」と、成人儀式として「胎内くぐり」があります。
幡祭りに初めて参加する者は全て「権立(ごんだち)」といい、衣装は母親などが着た花模様の襦袢か赤地の着物で、必ず「太刀」と「袈裟」をつけ、太刀は男根を象ったものを携えます。
「出立式」が木幡第一小学校の校庭で行なわれ、このあと幡を持って走る速さを競う「幡競争」の他に「木幡音頭踊り」や「東和太鼓」、餅つきなどが行なわれます。
このあと再び整列して、総大将が前に立って万歳三唱があり、続いて各堂社による餅撒きを行ないます。
これより出立で、緩い坂道を登って一旦参宿所に向かい、行列の途中にも餅を撒きます。

幡行列本隊は一旦参宿所を出立し、市道・林道を進み、さらに尾根を登り、鷹取場で休憩をし、約3kmの道を羽山神社へ向かいます。
幡の一行は神社に到着すると、大岩に幡を立てかけ、祝詞を唱えて参拝を行ないます。
権立の一行は、幡行列より一足先に羽山神社下の「胎内くぐり岩」を目指します。
神社の手前に胎内くぐりの岩があり、先達の指示で太刀と袈裟を納め「胎内くぐり」と言われる儀式を行ないます。
権立は小銭をくわえて岩の割れ目をくぐり、小銭を落としそっと手で拾う。このお金は羽山神社を参拝の際に使います。
全員がくぐり抜けると岩の前に並び、くぐり岩の一段上の大岩にもう一人の先達が、副大将がくぐり岩の前に立ち問答をする。
この儀式を「権立よばり」と言います。
羽山神社に到着した権立は、粥小屋で氏子に小銭を渡し、乳(粥)を御馳走になる。
これを「食い初め」と言います。
権立の羽山神社での参拝の際の拝み方は、神社に背を向け拝む「背拝み」、左側を向いて拝む「横拝み」、最後に正面の神社を向いて拝む「正面」と三回行います。
「羽山籠り」とは数日夜に渡り、籠り堂や堂社と言われる所で寝食をする行事で、参加出来るのは男性のみ、参加年齢は15歳以上である。
籠りにかかせない儀式として「水垢離」と呼ばれるものがあり、幡祭り前夜に折越堂社と当番の堂社、及び隠津島神社二の鳥居手水屋のみで行われていて、 白鉢巻と下帯のみになり手桶で水をかぶり身を清めます。